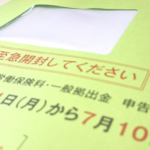この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。
社会保険料とは、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(40歳以上の場合のみ)」のことです。
これらの「社会保険料」の仕訳って・・意外と悩ましいですね。
「会社負担」と「個人負担分」があり、しかも「給料締め日」や「社会保険支払時期」で頭がごっちゃになることも多いかもしれません。
そこで今回は、「社会保険料」の簡単な会計処理と、発生主義での会計処理等をまとめます
(なお、広義の「社会保険」には「労働保険」も含まれます。労働保険の会計処理については、(Q14)をご参照ください)
1.会社と個人の負担割合は?
社会保険は、基本的には「会社と個人の折半」で負担します。
ただし、「子ども・子育て拠出金」については、会社全額負担となります。
2.年金事務所支払時期・給与締め日との関係は?
(1)年金事務所への支払時期は?
「年金事務所への支払時期」は決められています。当月分を翌月末に支払います
例えば、11月分の社会保険料は、12月末に支払います。
月の途中入社でも日割りせず、月末に在籍する方は、月額満額支払が発生します。
(2)給与締め日は?
「給与締め日」は、会社によってばらばらです。①当月分「当月払」の会社もあれば、②当月分「翌月払い」の会社もあります。
(3)両者の関係
「給与締め日・支払時期」と「年金事務所への支払時期」は全く連動していません。
社会保険の「従業員負担部分」は給料から天引しますので、社会保険の会計処理にあたって、このあたりが・・頭が混乱する理由なんだと思います。
3.勘定科目・会計処理は?
社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)となりますが、従業員負担分は、あくまで預り分のため、「費用」とはなりません。
会社負担部分は、「法定福利費」で処理を行います。
一方、従業員負担部分は、「法定福利費」を利用する場合と、「預り金」を利用する場合との2パターンあります。
| 会社負担分 | 法定福利費 |
|---|
| 従業員負担分 | 法定福利費or預り金 |
|---|
(1)従業員負担部分を「法定福利費」で計上する方法(簡単)
一番簡単な方法です。従業員負担分につき、給料天引時は「法定福利費(貸方)」で計上し、会社から年金事務所支払時は、全額「法定福利費(借方)」で計上する方法です。
上記の通り、社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)となりますが、従業員負担分は費用とはなりません。
そこで、従業員負担分を預かった際は、「法定福利費のマイナス」で計上し、従業員等負担分も含めた年金事務所への支払額(会社負担+従業員負担)全額を「法定福利費」として計上することで、借方と貸方が相殺され、結果的に「会社負担分」のみが「法定福利費」で計上される方法です。
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 毎月給料から預り時 | 給料 | 10,000 | 現金
法定福利費(社保) | 8,500
1,500 |
|---|
| 年金事務所支払時 | 法定福利費(社保) | 3,000 | 現金 | 3,000 |
|---|
(2)従業員負担部分を「預り金」で計上する方法(やや難)
従業員負担分につき、給料天引時は「預り金」で計上し、会社から年金事務所支払時は「預り金」を取り崩す方法です。
年金事務所への支払は、「会社負担分」も含めて支払いますので、支払時は、「預り金」の取り崩しだけではなく、会社負担分は「法定福利費」として計上します。一番スタンダードな方法だと思います。
| 借方 | 貸方 |
|---|
| 毎月給料から預り時 | 給料 | 10,000 | 現金
預り金(社保) | 8,500
1,500 |
|---|
| 年金事務所支払時 | 預り金(社保)
法定福利費(社保) | 1,500
1,500 | 現金 | 3,000 |
|---|
4.従業員からはいつ天引き?
(1) 給料から天引きする時期
従業員給料から天引きする方法は、以下の2つがあります。
| 翌月徴収(原則) | 当月従業員負担分を、翌月支払給与より徴収 |
|---|
| 当月徴収(例外) | 当月従業員負担分を、当月支払給与より徴収 |
|---|
原則は、「翌月徴収」となります。
なお、従業員からの徴収方法のどちらを採用しても、年金事務所への支払い時期が変わるわけではありません。例えば、11月分社会保険の年金事務所への支払いは、翌月徴収であれ当月徴収であれ、12月末までに納めなければいけません。
頭が混乱する理由は・・この「従業員から徴収する時期」と、「社会保険支払時期」がごっちゃになるからでしょうね。
(2) 具体例
翌月徴収を前提に、給料締め日ごとの「従業員負担部分」の天引時期をまとめると、以下の通りとなります。
(例 11月分の社会保険料(12月末に年金事務所に支払))
| 月末締 翌月25日払の会社(当月分翌月払) | 12月25日払給料から天引き(11月分給料) |
|---|
| 20日締 当月25日払の会社(当月分当月払) | 12月25日払給料から天引き(11/21~12/20分給料) |
|---|
「給料」の締め日に関わらず、年金事務所に社会保険を支払う月(前月分)と同じ月に支払う給料から「天引きする」という理解をすればよいです。
なお、当月分当月払いのケースでは、最終給料で社会保険が引き切れない場合があります。
月末退職時の場合は、2か月分を差し引くことが認められています。詳しくは、こちらをご参照ください。
5.具体例(翌月徴収)
(例題)
●給料計算期間は1日~31日、当月分を翌月25日に支給。
●社会保険料は、「翌月徴収」とします。
●給与天引きは、社会保険のみ(所得税、労働保険等の天引きは省略)
●給料額面40、社会保険料8(会社負担4 従業員負担4)、(簡便的に、会社負担、従業員負担は同額とします)
(1) 現金主義の場合(中小企業はコッチ)
中小企業の場合、社会保険の処理は、給与天引時と社会保険支払時に「仕訳」を行う場合が多いです。
従業員預り分の勘定科目を、①「法定福利費」で行う場合、②「預り金」で行う場合の2パターンがあります。
楽な方は①、従業員からの「預り金」をしっかり管理したい場合は②を利用します。
税務上は、どちらでも問題ありません。
●10月計上、11月支払の例を記載します。
●表内のカッコ書きは、社会保険該当月を示しています。
| | ①従業員預り分を法定福利費で計上 | ②従業員預り分を預り金で計上 | |
|---|
| 月 | 内容 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
|---|
| 10月末 | 給料計上 | | | | | 未払時点で、翌月支払社会保険料を預かっておく。 |
| 11月25日 | 給料支払 | | | 同左 | |
| 11月末 | 社保支払 | | | | | 年金事務所への支払は共に前月分(10月分)。 |
| 11月末 | 給料計上 | | | | | 10月と同様。以下同じ仕訳続く |
●②「預り金」を利用する場合、毎月末に1か月分の預り社会保険料が「預り金残高」で残ることになります。
(2) 発生主義の場合(上場会社等はコッチ)
| | ①従業員預り分を法定福利費で計上 | ②従業員預り分を預り金で計上 | |
|---|
| 月 | 内容 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
|---|
| 10月末 | 給料計上 | | | | | 未払時点で、翌月支払社会保険料を預かっておく。 |
| 10月末 | 社保計上 | | | | | 発生主義は法定福利費を未払計上 |
| 11月25日 | 給料支払 | | | 同左 | |
| 11月末 | 社保支払 | | | | | 年金事務所への支払は共に前月分(10月分)。 |
| 11月末 | 給料計上 | | | | | 10月と同様。以下同じ仕訳続く |
| 11月末 | 社保計上 | | | | | 10月と同様。以下同じ仕訳続く |
●発生主義では、月末に翌月支払予定社保を「未払計上」します。①の場合は、「従業員負担分+会社負担分」合計8を計上し、②の場合は、「会社負担分」4のみを計上します。
●②「預り金」を利用する場合、毎月末に1か月分の預り社会保険料が「預り金残高」で残ることになります。
6.社会保険料の更新時期
(1) 更新時期
毎年、9月分の社会保険料より、標準報酬月額が更新されます。9月分社会保険料の年金事務所への支払は、10月末です。
郵送で送られてくる「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を見て、標準報酬月額より、社会保険料の金額変更を行います。
(2)従業員から天引きする額を変更するタイミング
「翌月徴収」を前提とする場合、「更新後の社会保険料」を従業員給料から徴収する時期は、以下の通りとなります。
| 当月分翌月払の場合 | 9月分10月払給料 |
|---|
| 当月分当月払いの場合 | 10月分10月払給料 |
|---|
「変更後の社会保険料を年金事務所に支払う月」と「同じ月に支払われる給与」から天引きする、と考えれば・・わかりやすいかもしれません。
7.YouTube
YouTubeで分かる「社会保険料の会計処理」
関連記事